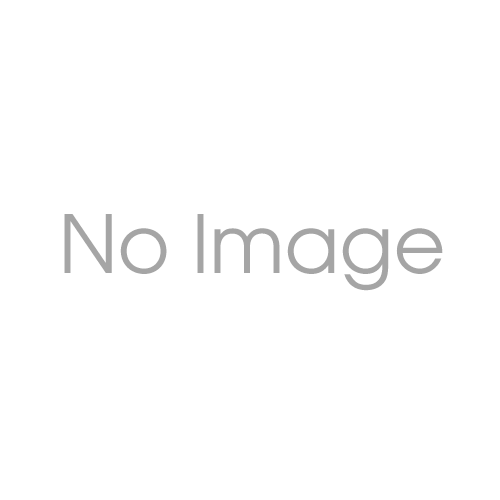サービス経営学部藤野ゼミの3,4年生が武州工業株式会社を訪問

サービス経営学部の藤野洋教授(専攻:中小企業論、持続可能な開発目標(SDGs))と藤野ゼミの3年生2人と4年生1人が2025年9月1日にゼミで行っている論文作成のための情報を聴取する武州工業株式会社(東京都青梅市)を訪問しました。
同社への藤野ゼミの学生の訪問は2023年の4年生、2024年の2年生に続いて3回目になります。
2023年:サービス経営学部藤野ゼミの4年生が卒業論文の研究で武州工業株式会社を訪問
(/topic/news/a138)
2024年:サービス経営学部 藤野ゼミの2年生が武州工業株式会社を訪問
(/topic/news/a213)
同社は、自動車用や医療機器用の金属パイプ部品、半導体製造装置の筐体などの生産を行っており、ICT(情報通信技術)やAI(人工知能)の活用など、様々な取り組みで高い生産性の実現していることなどで、多くの表彰を受けている企業です。
最初に、先代社長である林 英夫相談役から、当社の概要について「新市場進出を支える経営戦略とDX~カーボンニュートラルに向けて~」とのタイトルで、あらかじめお知らせしていた学生からの質問へのご回答を含めて、ご説明をいただきました(抜粋:順不同)。


(向かって右側奥が林相談役、手前が学生)
?「地域の雇用を守る」という使命感を持っており、そのためには利益を計上し続けること、そして納税することが重要と考えている。当社は黒字経営を50年以上連続しており、優良申告法人として税務署から7回表敬されている。当社を管轄する立川税務署の管内には1万8千社の法人があり、直近で表敬を受けたのは78社。7回表敬を受けたのは当社を含めて2社である。
?当社の製品は、かつては金属パイプを加工する自動車部品がほとんどだったが、パイプ加工の技術を生かして医療用機器(内視鏡?腹腔鏡関連)に進出した。さらに、コロナ禍の時期に自動車関連の生産活動がストップしたこともあり、近隣のトランスメーカーに従業員を派遣したことをきっかけにして、半導体製造装置関連にも販路を広げ、最近はパワーアシスタントスーツ等も手掛けている。
(注)右の写真の円グラフは緑が自動車部品、青が医療部品、水色が半導体、黄色がその他(汎用品)
現在の売上高は自動車部品が3割、医療用機器が5割、半導体製造装置が15%、残りがその他(汎用品等)となっている。今後は半導体製造装置関連とその他を伸ばそうとしている。
?当社は1カ月に900種類の製品を90万個生産しているが、例えば1台の自動車には1個しか使用されない。エンドユーザーに迷惑をかけるわけにはいかないので、最高級車でも軽自動車でも同じ品質の製品を作ることをモノづくりの基本としている。このため、不良品を最少化すなわち歩留まりの引き上げに力を入れている。
?現在日本の労働生産性は先進国で最低であるが、その背景には、日本の産業全体にいえることだが、「良いものを安く」というマインドが染みついていることがある。日本の産業?経済?生活水準を発展させるためには「良いものを適正な価格で」というマインドセットに切り替える必要がある。これには「適正価格」で販売しても利益を出せる競争力が必要であり、個々の企業が生産性を引き上げることが重要である。加えて、当社が既に様々な分野で力を入れているSDGsへの対応も日本だけでなく地球全体の持続可能性維持のために重要であり、これにも生産性向上が不可欠である。
?当社の特徴的な生産方式である「一個流し生産」は自社製のミニ設備という機械を半円状に配置して、その設備を技術者が加工手順に応じて操作する。いわば生産ラインを一人の技術者が多能工として担当している。さらに、材料管理、品質管理、出荷管理も一貫して対応している。このような事業全体のプロセスを「見える化」「効率化」するための「デザイン思考」によって、生産性向上を実現している。
(出所)同社Web

?「見える化」の過程で、特に従業員の製品検査の精度が昼食後に眠気が出る時間帯に下がることがわかった。つまり、人間による製品検査ではヒューマンエラーは取り除けないため、品質の閾値が上がりすぎ過剰品質による廃却品が増える。これを改善して生産性を向上させるために、AIによる不良品検出のシステムを開発?導入している。具体的には、複数のAIシステムを用いて不良品の検出を行っており、廃却品の減少を通じて資源の節約や環境保護などSDGsにも寄与している。
?従業員の福利厚生や生活にも配慮している。その例が「8.20体制」(1日8時間、1か月20日勤務で残業を無くし、休日をしっかりとりましょう)という社内活動を行っており、昨年度は1週間の途中の曜日の祝日も休日にすることによって年間稼働日数234日を実現した。自動車製造業では、ゴールデンウイーク、お盆、年末年始にまとまった休暇を従業員が取得するものの、電気炉?乾燥炉のような設備をいったん停止すると再稼働に時間?コストがかかるため、1週間の途中の曜日の祝日も稼働することが少なくない。234日というのは、年間3回のまとまった休暇に加えて、週途中の祝日も休業することで達成された。従業員にとって子供と祝日に行動できることからメリットが大きかった。特段の対策を講じないで週途中の祝日を休業にしたが生産性は低下しなかった。これは、多くの従業員が休業日増加によって生産性を低下させてはいけないとの意識で稼働日に勤務したことが原因と考えられる。
部署や年齢の垣根を越えて、従業員が交流して新たな発想を生み出すことを期待して、福利厚生やサークル活動にも気を配っている。
?生産性を高めるために、人材育成に力を入れている。事業内容の変化に伴い発生する余剰人員はロボットやAIの研究開発部門等に配属している。
さらに、利益の半分は期末賞与として従業員に還元している。

そのために、DX戦略がますます重要になっている。2025年3月に改訂した「武州工業株式会社 DX戦略2025」では、BIMMSを用いた①「よい設計、よい流れ」を核にすえたお客様サービス&製品の提供、②GKC(現場改善会計)を用いた改善効果の可視化と管理指標の設定、③デジタル人材の育成、④外部システムとの連携、を柱としている。
?この中のGKC(現場改善会計)とは、製造現場の改善活動と会計情報を連携させ、コスト削減や生産性向上の効果を数値化?可視化する手法であり、現場主導の経営判断を促進し、継続的な改善を支援する考え方である。2025年8月に京都大学で開催された日本原価計算研究学会の第51回全国大会ではGKCの研究者である愛知工業大学経営学部の柊紫乃教授と共同で行っている「DXによるジャスト?イン?タイム損益計算構築に関する探索的研究 武州工業株式会社の実践を事例として」に関する発表を行った。
?今後、社内の500か所に設置したタブレット端末等のIoTシステムから収集したビッグデータ等もを基に、「ジャスト?イン?タイム損益計算」、つまりリアルタイムでの損益把握が可能なシステムの構築を目指していきたい(AIによる解析も今後考えられる)。
?同時に、生産性向上のためには、共通EDIなどを通じて販売先との情報共有を促進し、さらなる品質、コスト、納期の向上を目指すことも重要な課題と考えている。そのために、情報セキュリティを担保しながら、外部取引先との情報共有するためのプラットフォームを構築することが課題であり、2027年には完了させたいと考えている。
当社の将来像としては、これまで社内での活用を前提と開発していたミニ設備や各種のシステムを外部に本格的に販売することも考えられる。現時点では、自動車、医療、半導体、その他(汎用品)の「ものづくり」が事業の主たる領域となっているが、社内外の知恵?情報?技術を連携して、飽くなき生産性向上を追求することが発展のために必要と考えている。
(林相談役のご案内による本社工場の見学)

ご説明の後に、本社工場を林相談役にご案内いただき一個流し生産やAIによる不良品検出の現場や半導体製造装置関連の最新鋭の板金関連の機械設備などを見学しました。その過程で、社内での人材育成の実態と同社の生産体制が絶え間なく高度化している様子がわかり、同社の高い生産性につながっていることもわかりました。
工場見学後には、学生との間で質疑応答と意見交換を行い、林相談役から丁寧なお答えをいただきました。その中に、AIによる不良品検出の精度について、以下のようなお話しがありました。
?当社では当初、1万個のサンプルでAIによる不良品検出を始めた。その後、日常的な生産活動によるデータの蓄積によって、検出の精度向上を目指しているが、不良品(NG)と合格品(OK)を完全に区分けすることは困難。
?当社としては、AIシステムが不良品と判定したが実は人間の再検査で合格品となる製品については廃却すれば販売先の迷惑にはならない。一方、AIが合格品と判定した製品の中に不良品が混入することは避けなければならない。この部分にAI活用のむずかしさがあり、人間がAIを常に「育てる」努力をすることが重要性である。
(林相談役からの質疑応答に関するご説明)
林相談役をはじめとする武州工業株式会社の皆様のご厚意で、訪問した学生は、地域の企業の経営と生産活動の現場を直にみるという貴重な経験と論文作成の練習にとって参考になる多くの学びを得ることできました。
なお、同社については、藤野教授が紹介した以下の記事もご覧ください。
「人材育成とICTで飛躍 高生産性サプライヤー」元気das® biz2022年9月20日発行(編集?発行所/㈱シーズン元気das® biz編集室)
(リンク)https://season-inc.net/genkidasbiz/220920/kirameki.html